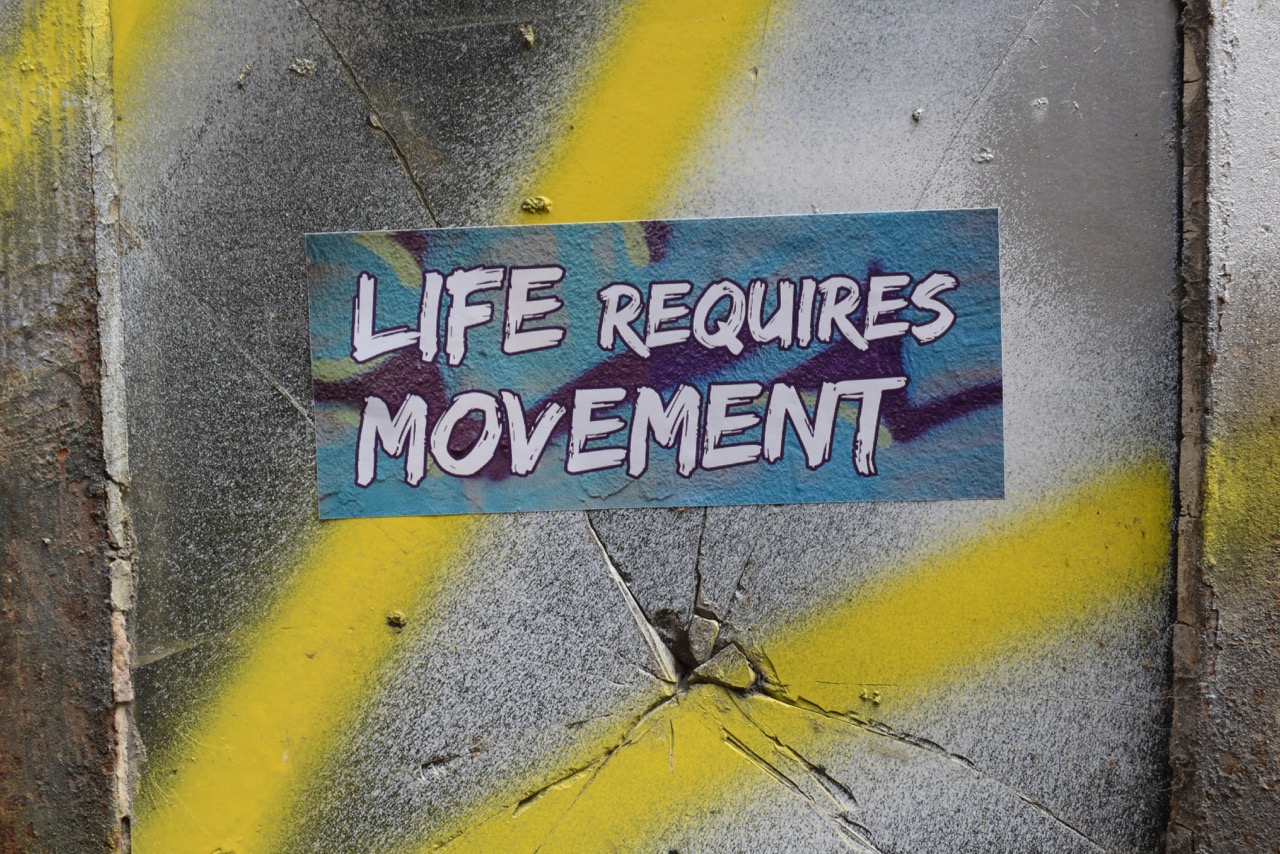本記事は、違法薬物の所持・使用を推奨するものではありません。
薬物の所持・使用については、当該国の法律・政令に従ってください。
CBD(カンナビジオール)と法規制 - 最新状況と国際比較(2025年版)
公開日: 2025/01/24
更新日: 2025/12/19 20:00

CBDをめぐる法規制の今
国内外で注目を集めるカンナビノイド成分、特に CBD(カンナビジオール)。日本では「茎・種子由来だから合法」という古い情報が広く出回っていますが、実際には法制度が大きく変化しており、旧情報のままでは誤解を招く危険があります。 本記事では、旧来の規制枠組みから、2024年12月の法改正、新制度のポイント、専門家の見解、そして海外との比較まで多角的に整理します。
旧制度のCBD規制、部位による合法・違法の区分とは
旧制度と「部位規制」の考え方
かつてのCBD関連の法制度は、いわゆる「部位規制」に基づいて運用されていました。大麻取締法(1948年制定)では、「大麻植物(Cannabis sativa L.)およびその製品」が規制対象とされていましたが、実務上は「葉・花穂・根およびその製品」が重点的に規制され、「茎・種子およびその製品」は除外されてきました(USDA Apps)。
このため、「茎や種子から抽出されたCBDは合法」「CBD成分を含んでいれば規制対象外」という理解が広く浸透しました。実際、CBD成分そのものは法令上、明示的な規制対象物質ではなく、「THC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていなければ合法」とする実務的な整理が行われていたのです(morihamada.com)。
しかしその一方で、輸入や販売の現場では多くのグレーゾーンが存在しました。たとえば、製品が「どの部位から抽出されたか」を証明する「部位由来証明書」の提出や、「葉・花が混入していないか」の検査確認などが求められるなど、実務的なハードルは決して低くありませんでした。
旧制度が抱えていた課題と限界
このような「抽出部位=安全」という単純な構図には、多くの限界がありました。製造や流通の過程で異なる部位が混入するリスクが無視されていたほか、特にTHC残留量についての明確な数値基準が設けられていなかったため、事業者にとっても「完全に合法」と言い切れる状況ではなかったのです。
さらに、古い情報がそのまま流通し続けることで、消費者や販売事業者が知らずに法的リスクを負うケースも少なくありませんでした。結果として、この旧制度の整理では、急速に発展するCBD市場や国際的な流通の実情に対応しきれなかったのです。
2024年12月の大麻取締法改正で何が変わったのか
法改正の背景にあった課題と国際的な動き
制度が大きく動いた転換点と、その背景を整理します。
厚生労働省(MHLW)など関係機関は、医療用途でのカンナビノイド研究や国際的な流通の拡大を受け、旧制度のままでは対応しきれない課題を抱えていました。研究開発や医薬品化、産業利用といった分野での法的な制約が、国内のCBD・ヘンプ産業の発展を阻む要因となっていたのです(DIA Global Forum)。
さらに、世界各国では大麻・ヘンプ由来製品の流通や規制の見直しが進み、合法化や基準緩和が相次いでいました。こうした国際的な変化の中で、日本でも産業振興、輸出入の円滑化、消費者保護といった観点から制度を再構築する必要性が高まっていったのです。
主な改正ポイント
以下の表に、改正前後の大枠を整理しました。
| 項目 | 改正前(旧制度) | 改正後(2024年12月12日〜) |
|---|---|---|
| 規制軸 | 部位(葉・花等=×、茎・種子=〇) | 成分(特に THC 含有量による基準) (大麻取締法) |
| 医療・製薬利用 | 大麻由来製品の医薬品承認なし | 医療用大麻製品の可能性を制度として明記 (麻薬及び向精神薬取締法) |
| 罰則強化 | 所有・輸入・栽培に対する規制中心 | 使用も禁止対象とし、罰則強化(例:所持・使用で最大7年懲役) (MHLW) |
| THC残留基準 | 明確な数値基準なし | 油・粉末・溶液など形態別に THC 残留数値基準が提示(10ppm/1ppm等) (MHLW) |
特に注目すべきは、「部位ではなく成分」という規制軸のパラダイムシフトです。これにより、茎・種子由来であっても THC 含有が基準を超えていれば違法となる可能性が明確化しました。
CBD製品の合法・違法を分けるポイント、THC残留基準と実務対応
実務的に事業者・消費者が理解すべきポイントを整理します。
THC残留基準の例
- 油・脂肪含有製品:10 ppm(10 mg/kg)以下
- 溶液(水系飲料など):0.1 ppm以下
- その他(食品・粉末等):1 ppm以下
このように、形態ごとに残留 THC のハードルが設定されており、日本は世界的に見ても非常に厳しい基準を課しています。 (Business of Cannabis)
事業者と消費者が押さえておくべき実務上のポイント
まず重要なのは、製品が「許可部位(茎・種子/成熟茎など)由来」であるという理由だけで安心しないことです。実際の合法・違法の判断は部位ではなく成分に基づいて行われるため、成分分析証明書(COA:Certificate of Analysis)を確認し、THC残留量が基準値内であることを必ず確かめる必要があります。
また、輸入・製造・販売を行う事業者は、法改正後に厚生労働省などから発出される最新のガイドラインや通知を継続的にチェックすることが求められます。
さらに、マーケティングや広告においては表現にも十分な注意が必要です。日本国内では「医薬品」や「治療効果」を示唆する表現でCBD製品を宣伝すると、薬機法や景品表示法に抵触するおそれがあります。
専門家が語る日本のCBD規制と海外との比較
国内の動きだけでなく、海外・専門家の意見も併せて抑えましょう。
専門家の見解
- Yasuta Arashiro 弁護士(日本の CBD 法務専門)によれば、「日本では広告規制・成分検査・輸入審査が極めてハードルが高く、特に海外企業の成功例はほとんどない」と指摘されています。 (Tokyoesque - Globally Aware & Curious)
海外比較、アメリカを例に
- 米国では、連邦レベルでは CBD 製品の食品・サプリメントとしての分類は明確になっておらず、 Food and Drug Administration(FDA)は「食品・サプリとしての CBD を現時点で承認できない」と表明しています。 (AP News)
- つまり、米国では「ヘンプ由来 CBD で THC 0.3 %以下」というモデルが流通していますが、日本はそれよりさらに厳しい数値基準(例:0.001 %以下)を掲げています。
「違法と誤解されるCBD」が増えている
法改正後の日本では、CBD製品の合法・違法の判断基準が「部位」から「成分(THC含有量)」に切り替わりました。しかし、実際の現場ではこの新制度への理解が十分に浸透しておらず、本来は合法な製品であっても、捜査機関や行政担当者が誤って違法と判断してしまうケースが少なくありません。
たとえば、海外製のCBDオイルや食品などは、正式な分析証明書(COA)が付いていても、その形式や記載内容が日本の基準と異なるため、通関や検査の段階で「THC混入の疑いあり」とみなされることがあります。ところが、再分析を行うと基準値を下回っており、結果的に“合法製品を違法と誤認していた”という事例が複数報告されています。
こうした状況の背景には、地方レベルでの運用や検査体制の差、また旧来の「部位規制」の理解が一部に残っていることが挙げられます。つまり、現場の執行側の知識更新が追いついていないのです。そのため、消費者や事業者は違法リスクだけでなく、誤認によるトラブルや検査対応の負担にも備える必要があります。
現時点で重要なのは、「合法・違法の境界を正確に理解しておく」だけでなく、「その合法性を証明できるだけのエビデンス(COA、輸入証明、分析データなど)を備えておくこと」です。
古いCBD情報に注意、法改正後に誤解されやすいポイント
古い記事などでいまだに見かける内容の中には、すでに法改正で前提が変わっているものがあります。以下の表で、よくある旧情報と現在の正しい理解を整理します。
| 旧情報・誤解されやすい記述 | 最新の正しい理解(2025年時点) |
|---|---|
| 「種子や茎から抽出されたCBDは規制対象ではない」 | 以前は部位による除外論が主流でしたが、現在は成分基準(THC残留量)による判断に移行しています。 |
| 「CBDは規制対象物質には含まれていない」 | CBDそのものは依然として規制物質ではありませんが、製品中にTHCが含まれている場合は違法扱いとなる可能性が明確化されています。 |
| 「種子と茎、その製品を除外している」 | 旧法での“部位除外”の枠組みは、改正により実質的に廃止されました。 |
| 「2020年時点でTHCを含有する製品は原則輸入できない」 | 現在は分析基準やライセンス制度が整備され、単純に「輸入不可」ではないものの、より厳格な運用が行われています。 |
| 「大麻は全面禁止されている」 | 改正法により、医療用大麻の使用が制度的に可能となりました。厚生労働大臣の承認を受けた医薬品に限り、医療目的での使用が認められます。 |
| 「大麻取締法では“使用”自体は罪に問われない」 | 改正後は「使用罪」が新設され、所持・栽培に加えて使用も処罰対象となりました。THCを含む製品を使用した場合、最大7年以下の懲役となる可能性があります。 |
| 「産業用ヘンプの規制は従来通り」 | 産業用ヘンプ制度が見直され、用途制限型から成分管理型へ転換。栽培許可制度が改正され、産業利用の拡大が進められています。 |
過去に「使用罪」が存在しなかった理由大麻取締法が制定されたのは1948年(昭和23年)であり、その目的は現在のような乱用防止ではなく、主に産業用ヘンプの栽培や流通を管理することにありました。制定当時の日本では、大麻は繊維や種子油、神事用として利用されており、いわゆる「薬物」としての認識は一般的ではありませんでした。そのため、法律は「所持」「譲渡」「栽培」「輸入」などの行為を規制し、「使用」という行為を処罰の対象にする必要がなかったのです。
また、当時はTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分の分析技術が確立しておらず、「使用」という行為を立証することが非常に困難でした。麻繊維や油脂など合法的な大麻製品にも微量の成分が含まれる可能性があったため、使用を処罰対象とすると、正規の産業活動まで制限してしまう懸念がありました。このため、立法時には意図的に「使用罪」が除外された経緯があります。
さらに、他の薬物法(麻薬及び向精神薬取締法や覚醒剤取締法)と異なり、大麻取締法は「使用者を処罰する」よりも「無許可の所持や流通を防ぐ」ことに重点を置いていました。大麻は伝統的な文化や農業と結びついていたため、使用行為そのものを犯罪視する必要がないと考えられていたのです。
しかし近年、海外からのCBDやTHC製品の流入、医療用大麻の議論の高まり、所持を伴わない使用ケースの増加などにより、所持規制だけでは十分に対応できない状況が生まれました。このため、厚生労働省は「乱用防止の実効性を確保するためには、使用自体も処罰対象とする必要がある」と判断し、2024年12月施行の法改正で新たに「使用罪」(大麻取締法第24条の4)が設けられました。
つまり、従来の大麻取締法は「使用者を罰する」ことを目的とした法律ではなく、「生産・流通を管理する」ための制度でした。戦後の社会構造と技術的制約が背景にあり、これが長年「使用罪」が存在しなかった最大の理由といえます。
CBDを扱う人が確認すべきチェックリスト
消費者の視点、安全にCBD製品を選ぶためのポイント
| 確認項目 | 実践的なポイント(2025年時点) |
|---|---|
| 製品ラベルと表示 | 成分量、製造日、販売者情報、検査機関などラベルの透明性を重視する。 |
| ブランドと販売者の信頼性 | 日本国内の法令(改正大麻取締法)に準拠しているか、問い合わせ先・会社情報が明示されているかを確認。 |
| 海外製品・個人輸入の注意点 | 海外基準の「THCフリー」は日本の基準を満たさない場合がある。正規輸入ルートを選び、通関でのリスクを考慮する。 |
| 使用時の自己管理 | 少量から試し、体調や反応を記録しておく。違和感があれば使用を中止し販売者や専門家に相談。ラベルや購入履歴を保管しておくと安心。 |
事業者(輸入・販売・製造)の視点、遵守すべき実務ポイント
| 確認項目 | 実務上のポイント(2025年時点) |
|---|---|
| 製品の品質管理 | 原料・抽出部位・製造工程だけでなく、最終製品中のTHC残留量を定期的に検査し、COA(分析証明書)を保持・更新することが求められます。 |
| 広告・マーケティング表現 | 「治療」「効果」「医療用」などの表現は、薬機法・景品表示法に抵触する可能性があります。効能を示唆せず、成分や品質を中心に訴求するのが安全です。 |
| 法改正への対応 | 厚生労働省の通知や通達、自治体のガイドラインを定期的に確認し、制度変更に即応できる体制を整えることが重要です。 |
| 国際展開・輸出入戦略 | 日本は世界的にも最も厳しいTHC基準を採用しており、海外基準をそのまま適用するのは危険です。輸入・輸出いずれも基準差を考慮したビジネス設計が必要です。 |
まとめ、CBDの法規制は「部位」から「成分」へ転換した
CBD およびカンナビノイド製品の法的位置付けは、旧来の「部位規制」から「成分規制」へと大きく変化しました。 「種子・茎=安全」という旧情報はもはや通用せず、製品中の THC 残留量が合法/違法の鍵となっています。しかも、日本は世界的にも極めて厳しい基準を設けており、消費者・事業者双方にとって法的・実務的な注意が必要です。 今後、医療用カンナビノイド製品の承認やヘンプ産業の拡大も視野に入れられていますが、その流れに乗るためにも「制度理解」「成分分析」「表現規制」などをクリアにしておくことが重要です。
参考資料・リソース
関連法令リンク
カバーイメージ
- Photo by Brett Jordan on Unsplash
関連記事
|
CBD(カンナビジオール)と法規制 - 最新状況と国際比較(2025年版)
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-01-24 14:34
CBDをめぐる法規制の今
国内外で注目を集めるカンナビノイド成分、特に CBD(カンナビジオール)。日本では「茎・種子由来だから合法」という古い情報が広く出回っ…
|
|
|
2025年CBN規制事件 - 更年期・PMSの緩和が違法になる日
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-12-01 13:12
更年期の不眠、PMSの痛み。やっと見つけた「自分に合う方法」が奪われようとしています
2025年12月28日。この日付は、多くの女性たちにとって、自分の健康を…
|
|
|
大麻輸出ビジネスの実務 - Web3.0とトレーサビリティ
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-12-24 20:07
なぜ今、大麻輸出実務が注目されているのか
近年、医療用大麻および産業用ヘンプの世界市場は急速に拡大しています。Grand View Researchの2024年…
|
|
|
大麻及びサイケデリックの私的使用合法化研究会 - 年次レポート(所長報告)
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-12-29 11:42
はじめに
本研究会は、科学的根拠、公衆衛生、人権、社会的影響の観点から、大麻およびサイケデリックの私的使用に関する法制度の在り方を研究している。本年度は、海外に…
|
|
|
厚労省に「薬物乱用防止五か年戦略」の開示請求を出しました
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-09-07 17:28
今日は、「薬物乱用防止五か年戦略」第一次(1998–2002年)/第二次(2003–2007年)に関する文書について、厚生労働省へ情報公開法に基づく開示請求(不…
|
INGREDIENT 成分から探す
USAGE 使い方から探す
人気商品から選ぶ
-
CRDP 60% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
1Fe-LSD(1-フェロセニル-LSD) 200mcg【観賞用】 の商品詳細へ

- 1Fe-LSD(1-フェロセニル-LSD) 200mcg【観賞用】
- ¥5,500
- ACID / CAPS
-
CRDP 60% x CPX 30% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
MANGO LUXE H4CBH15% CRDB50% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
- CRDHとは?注目される新世代カンナビノイド成分の完全ガイド
- はじめに 近年、大麻由来成分に関する科学…
- 月間閲覧数:560
-
- 物質辞典 - H4CBHとは
- 現代のウェルビーイングを追求する中で、日…
- 月間閲覧数:309
-
- 海外 - ハワイのおすすめ大麻ディスペンサリー
- 目次 はじめに …
- 月間閲覧数:143
-
- 物質辞典 - CBXEとは
- 重要な前置き:本記事を執筆するにあたり、…
- 月間閲覧数:132
-
- 渋谷のディスペンサリーオーナーの自殺と日本の司法制度
- はじめに 2025年2月18日、渋谷のデ…
- 月間閲覧数:113
-
- 精製方法 - キーフの魅力と使い方を解説
- 大麻を愛する大人の皆さん、こんにちは。今…
- 月間閲覧数:108
-
- 物質辞典 - 1S-LSD(規制物質)とは
- 1S-LSDは、2025年3月15日に厚…
- 月間閲覧数:100
-
- CBD(カンナビジオール)と法規制 - 最新状況と国際比較(2025年版)
- CBDをめぐる法規制の今 国内外で注目を…
- 月間閲覧数:87