本記事は、違法薬物の所持・使用を推奨するものではありません。
薬物の所持・使用については、当該国の法律・政令に従ってください。
厚労省に「薬物乱用防止五か年戦略」の開示請求を出しました
公開日: 2025/09/07
更新日: 2025/09/21 17:38
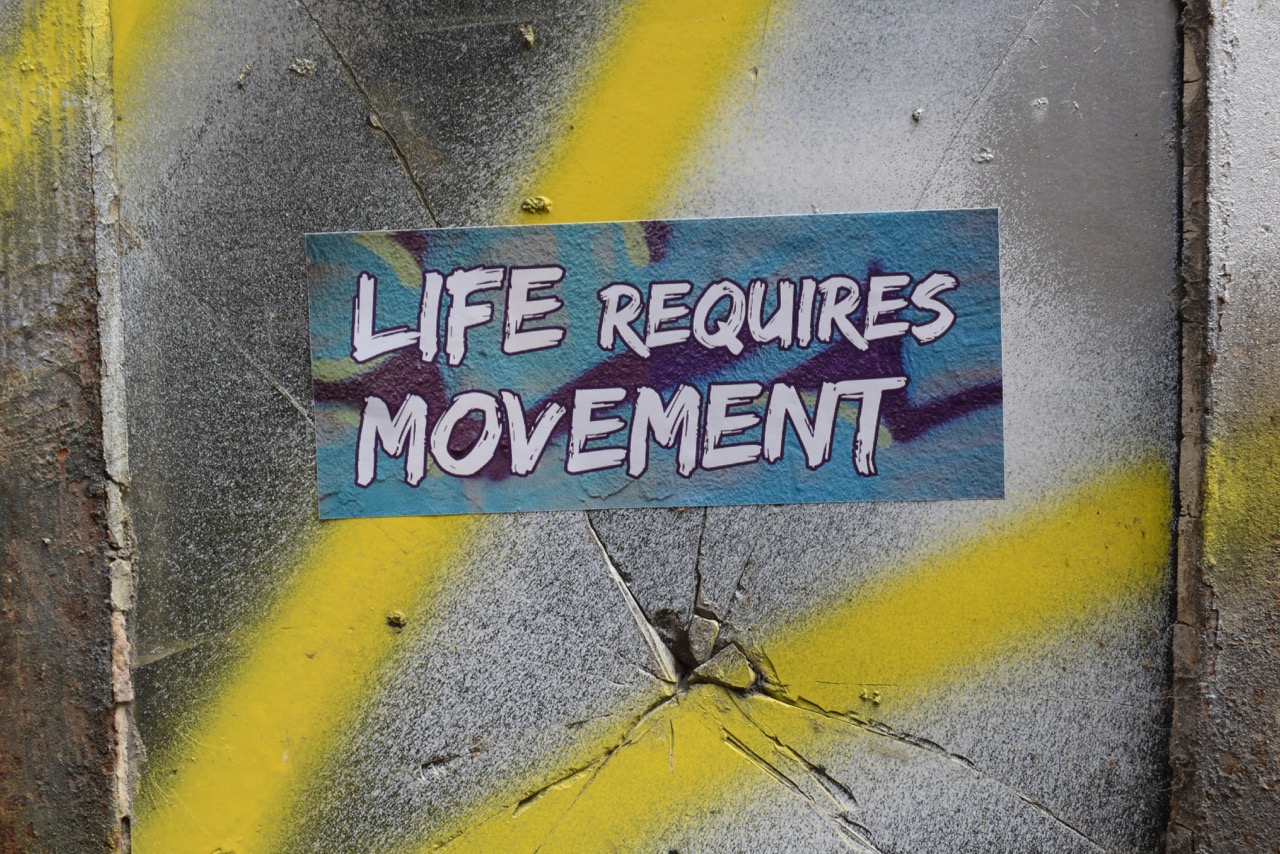
今日は、「薬物乱用防止五か年戦略」第一次(1998–2002年)/第二次(2003–2007年)に関する文書について、厚生労働省へ情報公開法に基づく開示請求(不存在確認を含む)を2025年8月30日付で提出したことをご報告します。
薬物乱用防止五か年戦略とは?
薬物乱用防止五か年戦略は、日本政府が 5年間を一区切りに、予防教育・啓発、取締り、水際対策、治療・回復支援、 国際連携までを包括的に進めるための中期計画です。政府一体の総合対策として、 社会情勢や乱用実態の変化に合わせて改訂が重ねられてきました。
その前段階としては、1992年に内閣に薬物乱用対策推進本部が設置され、 当初は急増する覚醒剤乱用を重点的に抑止することが狙いでした。 1993年頃には「薬物乱用防止行動計画」が策定され、学校教育や啓発活動が展開されましたが、 依然として焦点は覚醒剤対策に絞られていました。
そして1998年に初めて「薬物乱用防止五か年戦略」が策定され、 その対象は大麻・サイケデリック・ケミカル・危険ドラッグなどへと大きく広がりました。 取締りに加え、教育・治療・社会復帰支援・国際協力を含む包括的アプローチが明文化され、 政府全体で進める総合戦略として位置付けられたのです。
設立の背景
1990年代、覚醒剤乱用の深刻化や若年層の薬物問題が社会課題化。 包括的・中長期の対策が求められ、1998年(平成10年)に初の五か年戦略が策定されました。
担当体制・運営主体の推移
当初は、内閣府の「薬物乱用対策推進本部」が主管となり、 内閣府特命担当大臣(薬物乱用対策)だった有村治子氏が議長を務めました。 この枠組みの下で、省庁横断の総合対策が進められたのです。
その後、推進会議の構成や所掌の見直しを経て、現在は厚生労働大臣が議長となり、 関係閣僚で構成される「薬物乱用対策推進会議」の下で、 厚労省が中心となって総合対策を主導しています。
| 時期 | 主な統括体制 | 概要 |
|---|---|---|
| 1998年(平成10年)〜 | 内閣府・薬物乱用対策推進本部 (有村内閣府特命担当大臣が議長) |
初の五か年戦略。省庁横断の推進体制を整備。 |
| 2010年代〜 | 推進会議の見直し・実務分担の再整理 | 依存症支援や教育・医療分野の比重が高まり、厚労省の役割が拡大。 |
| 2023年(令和5年)〜(第六次) | 厚生労働大臣が議長の薬物乱用対策推進会議 | サイバー空間での密売、水際対策、再乱用防止等を重点に、 厚労省主導で政府横断の実行管理。 |
文書開示請求までの経緯
- 「薬物乱用防止五か年戦略」第一次(1998–2002年)および第二次(2003–2007年)の資料について、私たちは内閣府に確認しました。その結果、かつて戦略策定に関与していた「薬物乱用対策推進本部」はすでに廃止されており、後継組織も内閣府に存在しないことが判明しました。
- さらに、内閣府からは「薬物乱用防止五か年戦略」に関する資料はすべて厚生労働省に引き継いでいるため、現在の照会先としては厚生労働省が適切であるとの案内を受けました。
- 同資料について厚生労働省に確認したところ、「保管期限経過により当該資料は破棄済み」との回答を得ました。
- その後、私たちは顧問弁護士と協議し、「関連一切の資料(申し送り等を含む)」を広く対象とする公式な開示請求(文書不存在の明文化を含む)が将来の議論基盤として有用であるとの結論に至りました。
- 2025年8月30日、私たちはその方針どおり正式に開示請求を行いました。結果は追って公開します。
なぜ今、開示請求なのか:大麻の国際評価の“リスク格下げ”が起点
五か年戦略以前から継承される「乱用」の定義
日本の政策文書で用いられてきた「乱用」という概念は、1990年代前半の 薬物乱用対策推進本部の時代から「正当な医療目的以外の薬物使用」を指すものとして使われてきました。(「薬物乱用とは、医薬品を医療以外の目的で使用すること、医療目的ではない化学物質を不正に使用すること」国立教育政策研究所(指導資料)、「薬物乱用とは、ルールや法律から外れた目的や方法で使用すること」厚生労働省)
当初は急増する覚醒剤乱用を抑止することが主眼でしたが、 1998年の薬物乱用防止五か年戦略の策定により、 大麻・サイケデリック・ケミカル・危険ドラッグなども含めた包括的な対象へと拡張されました。
「スケジュール変更」による大麻のレーティングが下がったことの意味
- 国連の1961年麻薬単一条約では、薬物そのものの危険性と医療的価値に基づいてスケジュール(区分)が設定されています。その中で、Schedule Iに該当する薬物のうち、特に有害で医療的価値が乏しいものは、さらにSchedule IVという最上級ラベルが付与されていました。
- 2020年12月、国連薬物委員会(CND)は大麻・大麻樹脂をSchedule IVから外すことを決定しました。これにより「特に有害で医療的価値が乏しい」という最上級のラベルが外れ、危険性レーティングが一段下がったと理解できます(ただしSchedule Iには残存)。すなわち「最も厳しい追加指定が解除された」=大麻に一定の医療的有用性が国際的に認められたということです。 (UNODC, World Health Organization)
例えるなら、危険物に貼られていた赤い“最上級の警告シール”が剥がれ、通常の警告シールだけになった。──というイメージです。
日本では1990年代前半から医療利用を認めていないため大麻は自動的に「乱用」と見做されている可能性があります。一方、国際的には大麻の医療的有用性が認められています。したがって、国のこの「乱用」という定義をそのまま大麻に適用し続けることは、国際評価との間に明確な矛盾を生みます。この矛盾を検証するためには、日本の政策文書における「乱用」や「有害性」の扱いを一次資料で確認することが不可欠であり、仮に資料が不存在であれば、その事実を公式文書(不存在通知)として残すこと自体が後日の政策議論で重要となります。
国際評価の変化
| 時期 | 国際区分 | 変化 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 変更前(1961~2020年) | Schedule I + Schedule IV | 「特に有害で医療的価値が乏しい」という最上級ラベル付与 | 医療用途を正当化する余地がほぼなかった |
| 変更後(2020年12月~) | Schedule I のみ | Schedule IVから除外 | 最上級ラベルが外れ、医療的有用性が認知 |
補足解説
2020年12月の国連麻薬委員会(CND)決定で、大麻と大麻樹脂は「特に有害」とされるSchedule IVから外れました。これにより国際的に「医療的価値の可能性がある」と認められました。実際、2025年現在、大麻を合法化または非刑罰化している国・地域は約50に達しています。
国際基準に追随するための最新海外動向(2025年8月調べ)
米国連邦政府は2024年に大麻をSchedule I→IIIへ移行する規則案を公表し、意見公募・公聴会などの手続を進めています(最終決定は未了)。Schedule IIIは「医療用途を認め、Schedule I/IIより乱用可能性が低い」区分。移行しても連邦での“合法化”ではなく、CSA(連邦麻薬法)やFDAの枠組み下に置かれる点は変わりません。 (Federal Register, Department of Justice)
2025年8月時点の米政策センター(OSU)整理でも、HHSの科学的評価 → DEAによるSchedule III提案 → 規則制定手続進行中の流れが確認できます。つまり、「医療的有用性が認められる」方向へ舵が切られているのは確かですが、連邦レベルの全面合法化ではないことに注意が必要です。 (Moritz College of Law)
なお、“スケジュール変更=直ちに合法化”ではないことは、米シンクタンクBrookingsも一貫して指摘してきました。制度上の誤解を避けるためにも、この区別は重要です。 (Brookings)
米国の動き:「スケジュールIII」案とその論点
米国連邦政府は2024年に大麻をSchedule IからSchedule IIIへ移行する規則案を公表し、DEAが手続きを進めています。Schedule IIIは「医療用途を認め、乱用可能性は低い」とされる区分で、研究や税制(280E条の撤廃)への影響が大きいと見られています。ただし、これによって私的使用が直ちに合法化されるわけではなく、連邦法の規制枠組み下に残る点は変わりません。
| 組織 | 正式名称・役割 | 決定の効力 | マリファナへの影響の仕方 |
|---|---|---|---|
| HHS | 米保健福祉省(U.S. Department of Health and Human Services) FDAやNIHを所管し、医学的・科学的評価をDEAに勧告 |
法的拘束力はないが重い影響力を持つ。HHSの勧告に基づきDEAが最終決定を行う | 例:2023年に「大麻をSchedule IIIへ移行すべき」と勧告。DEAの規則案につながった |
| 米政策センター(OSUなど) | Oregon State University Drug Policy Centerなど大学・研究機関 政策・科学的分析を行い、連邦・州の議論に学術的根拠を提供 |
直接の規制権限はないが、議会・世論・行政判断に影響 | 例:研究データや政策提言を通じ、HHSや州政府の議論を後押し |
| DEA | 米国麻薬取締局(Drug Enforcement Administration) 司法省の下にある国内法執行機関 |
米国内の連邦法上の規制に直結。スケジュール変更は税制・研究許可・処方実務にすぐ影響 | 例:Schedule I→IIIなら、研究環境改善・医療用途承認・税制280E条の適用解除 |
| CND(国連麻薬委員会) | Commission on Narcotic Drugs。国連加盟国が条約に基づき薬物の国際スケジュールを決定 | 国際条約レベルでの義務。各国は国内法に反映する努力義務を負うが即効性は弱い | 例:2020年に大麻をSchedule IVから除外。ただし各国が法改正するまで実生活に直結しない |
| WHO/ECDD | Expert Committee on Drug Dependence(WHOの専門家委員会) | 科学的評価と勧告を行い、CNDに提出 | 例:2019年に大麻・大麻樹脂の再評価を勧告。最終決定権はCNDにある |
補足解説
ここで混同しやすいのが、国連組織との違いです。国連麻薬委員会(CND)やWHOの専門家委員会(ECDD)は国際的な「危険度ラベル」を決めたり勧告したりする場であり、各国はその決定を尊重する義務を負います。しかしそれはあくまで国際的なシグナルにすぎず、各国が国内法を改正しない限り直接の効果はありません。一方、DEAは米司法省の機関として、米国内で即効性のある法的・実務的変更を行います。したがって、DEAによる再スケジュール決定は、研究許可や医療利用、産業税制などに直結し、国連の決定よりも現実的な影響範囲が大きいのです。
専門家・研究者の見解
| 出典 | 主張・知見 |
|---|---|
| NASEM(米国アカデミーズ, 2017) | 慢性疼痛・化学療法悪心・多発性硬化症の痙縮に確かな効果。若年層や妊娠中の使用はリスク不明点が多い |
| David Nuttら(Lancet, 2010) | 薬物の有害性を比較し、大麻はアルコールやタバコより低リスクとする分析 |
| CDC(2024) | 高THC製品や若年期使用で精神病性障害リスクが高まる可能性を示唆 |
補足解説
科学的評価は「有効性」と「リスク」を両睨みしています。NASEMは医療的効果の確実な領域を明記しつつ、弱点や不確実性も指摘。CDCは若年者や高用量使用のリスクに注意を促しています。
- National Academies Report (2017)
- David Nutt et al., The Lancet (2010)
- CDC: Cannabis and Health (2024)
アドボカシー団体の立場
| 団体 | 主張 |
|---|---|
| Drug Policy Alliance | 刑事罰縮小と規制合理化を重視。合法化は目的でなく、公衆衛生・公平性・人権の実現手段 |
| NORML | 連邦法と州法の乖離が市民・産業にコストを強いるため、CSAからの除外(デスケジューリング)を推奨 |
補足解説
市民運動の観点では、単に「合法か非合法か」ではなく、刑罰・規制の合理化と公衆衛生の調和が焦点です。産業界にとっても、連邦法と州法のギャップは深刻な課題となっています。
まとめ
今回の開示請求で焦点にする論点
- 一次資料である戦略文書内で「乱用」「有害性」がどのように定義されていたか
- 「乱用(abuse)」の用語の定義が、WHOや国連などの国際基準と日本では異なるのか
- 国際評価の変化が、国内の表現や閾値(THC濃度等)に反映できる設計だったか
- 保存年限経過による「破棄」が常態化する中で、政策形成過程の透明性をどう担保するか
今後の当店の方針
今回のやりとりを受け、私たちは改めて情報公開請求を行い、文書不存在を公式に明文化する方向で進めています。
これは単なる形式的な作業ではなく、日本における「乱用」の定義がどのように作られてきたのか、その痕跡を記録として残す取り組みです。
大麻やサイケデリックをめぐる国際的な評価が変化していく中で、日本の政策も透明性と一貫性をもって議論されるべきだと考えています。今後も進展があれば、このブログで共有していきます。
- 開示結果(文書の開示/不存在通知)を受領次第、原文と要点を公開
- 「定義と根拠」「THC閾値」「若年者保護」「研究・税制」の4つのテーマで連載解説を展開
- 次回策定される第7次薬物乱用防止五か年戦略から大麻など医療的有用性が認められた物質を除外
参考資料・リソース
カバーイメージ
- Photo by Marija Zaric on Unsplash
関連記事
|
CBD(カンナビジオール)と法規制 - 最新状況と国際比較(2025年版)
公開:2025-01-24 14:34
CBDをめぐる法規制の今
国内外で注目を集めるカンナビノイド成分、特に CBD(カンナビジオール)。日本では「茎・種子由来だから合法」という古い情報が広く出回っ…
|
|
|
2025年CBN規制事件 - 更年期・PMSの緩和が違法になる日
公開:2025-12-01 13:12
更年期の不眠、PMSの痛み。やっと見つけた「自分に合う方法」が奪われようとしています
2025年12月28日。この日付は、多くの女性たちにとって、自分の健康を…
|
|
|
大麻輸出ビジネスの実務 - Web3.0とトレーサビリティ
カテゴリ:
法規制・行政
公開:2025-12-24 20:07
なぜ今、大麻輸出実務が注目されているのか
近年、医療用大麻および産業用ヘンプの世界市場は急速に拡大しています。Grand View Researchの2024年…
|
|
|
大麻及びサイケデリックの私的使用合法化研究会 - 年次レポート(所長報告)
公開:2025-12-29 11:42
はじめに
本研究会は、科学的根拠、公衆衛生、人権、社会的影響の観点から、大麻およびサイケデリックの私的使用に関する法制度の在り方を研究している。本年度は、海外に…
|
|
|
厚労省に「薬物乱用防止五か年戦略」の開示請求を出しました
公開:2025-09-07 17:28
今日は、「薬物乱用防止五か年戦略」第一次(1998–2002年)/第二次(2003–2007年)に関する文書について、厚生労働省へ情報公開法に基づく開示請求(不…
|
INGREDIENT 成分から探す
USAGE 使い方から探す
人気商品から選ぶ
-
CRDP 60% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
1Fe-LSD(1-フェロセニル-LSD) 200mcg【観賞用】 の商品詳細へ

- 1Fe-LSD(1-フェロセニル-LSD) 200mcg【観賞用】
- ¥5,500
- ACID / CAPS
-
CRDP 60% x CPX 30% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
MANGO LUXE H4CBH15% CRDB50% VAPEリキッド の商品詳細へ

-
- CRDHとは?注目される新世代カンナビノイド成分の完全ガイド
- はじめに 近年、大麻由来成分に関する科学…
- 月間閲覧数:560
-
- 物質辞典 - H4CBHとは
- 現代のウェルビーイングを追求する中で、日…
- 月間閲覧数:309
-
- 海外 - ハワイのおすすめ大麻ディスペンサリー
- 目次 はじめに …
- 月間閲覧数:143
-
- 物質辞典 - CBXEとは
- 重要な前置き:本記事を執筆するにあたり、…
- 月間閲覧数:132
-
- 渋谷のディスペンサリーオーナーの自殺と日本の司法制度
- はじめに 2025年2月18日、渋谷のデ…
- 月間閲覧数:113
-
- 精製方法 - キーフの魅力と使い方を解説
- 大麻を愛する大人の皆さん、こんにちは。今…
- 月間閲覧数:108
-
- 物質辞典 - 1S-LSD(規制物質)とは
- 1S-LSDは、2025年3月15日に厚…
- 月間閲覧数:100
-
- CBD(カンナビジオール)と法規制 - 最新状況と国際比較(2025年版)
- CBDをめぐる法規制の今 国内外で注目を…
- 月間閲覧数:87












