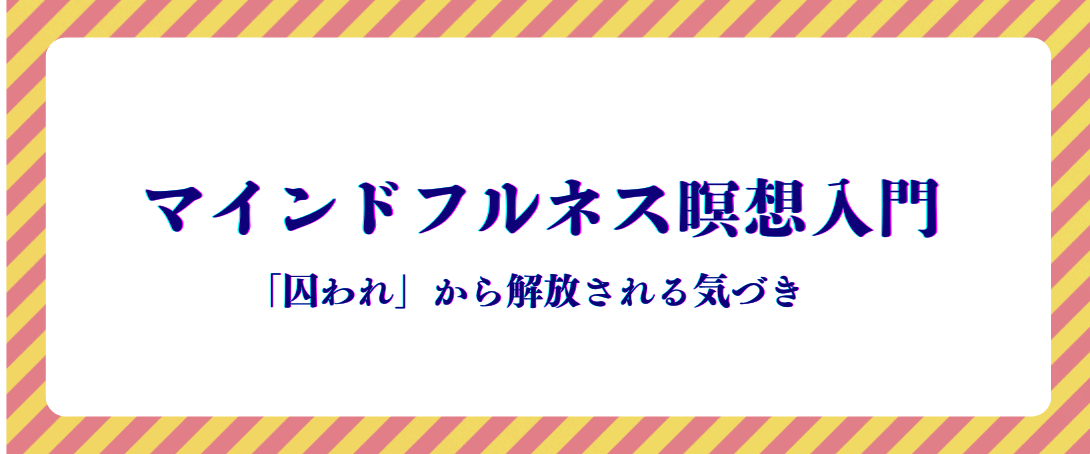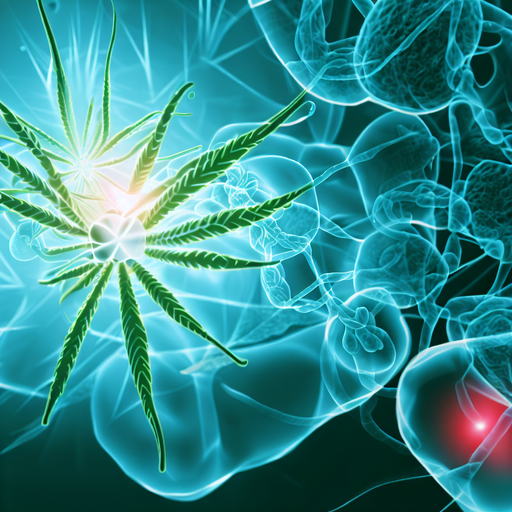本記事は、違法薬物の所持・使用を推奨するものではありません。
薬物の所持・使用については、当該国の法律・政令に従ってください。
教育者のための物質使用ガイド: 第2部「スティグマ(偏見)を理解する」
公開日: 2025/10/07
更新日: 2025/10/19 22:03

(※内容の改変・有償利用は行っておりません)
目次
- イントロダクション
- 学校、教育者、ユース支援者の役割
- 学習ユニットと教育者用ガイドについて
- 用語解説
- 第1部:物質使用を理解する
- 学習ユニット序文
- 青少年と物質使用
- 使用のスペクトラム
- 問題的使用と物質使用障害
- 脳の発達、物質使用、不利な幼少期体験
- レジリエンスを育み、害を減らす
- 教育者が青少年を支援する方法
- 追加リソース
- 第2部:スティグマ(偏見)を理解する
- 学習ユニット序文
- スティグマとは何か?
- 物質使用に関するスティグマとは?
- スティグマの種類
- スティグマの影響
- 言葉の重要性
- 教育者がスティグマをなくすためにできること
- 追加リソース
- 第3部:大麻のベイピングを理解する
- 学習ユニット序文
- カナダにおける青少年の大麻とベイピング
- 大麻の使用方法
- 大麻のベイピングとは?
- 大麻ベイピング製品
- 大麻ベイピングの害とリスクとは?
- 青少年のリスクを減らすための支援戦略
- 追加リソース
- 第4部:アルコールを理解する
- 学習ユニット序文
- カナダにおける青少年のアルコール使用
- 青少年の飲酒パターン
- アルコールとは何か?
- アルコール製品
- カナダ低リスク飲酒ガイドライン
- 青少年におけるアルコール関連の害とリスクの概要
- 青少年のリスクを下げるための支援戦略
- 追加リソース
- 第5部:能力障害運転を理解する
- 学習ユニット序文
- カナダにおける能力障害運転
- 能力障害運転と青少年
- 薬物が運転能力に及ぼす影響
- 能力障害運転のリスク・害・結果とは?
- 取締りと検知
- 教育者が青少年を支援する方法
- 追加リソース
- 支援とサービス
- 参考文献
学習ユニット序文
このセクションは、物質使用に関するスティグマ、その種類、スティグマが人々がケアを求めたり受けたりするのをどのように妨げるか、そしてスティグマを減らすために誰もが果たせる役割について情報を提供します。
まず「スティグマの理解」ビデオ学習ユニットを視聴し、その後に本セクションの演習に取り組んでください。
主要な概念と要点
- 物質使用スティグマは広く存在する。
- スティグマは3つのレベルで存在する:構造的、社会的、個人的(自己への偏見)。
- スティグマは複雑であり、複合的または交差的である場合がある。
- スティグマは有害であり、支援を求める障壁となる。
- 言葉は重要であり、言語は変化のための強力なツールである。
- 人を優先する言葉(person-first language)は、その人の状態ではなく人そのものに焦点を当てる。
- 教育者は、スティグマを伴わない言葉や行動を用いることでポジティブな影響を与えることができる。
注意
このセクションではスティグマとその人々への影響について探究します。一部の人にとっては、スティグマの経験を思い起こさせ、強いまたは苦痛を伴う感情を引き起こす可能性があります。このセクションの内容によって強い、苦痛を伴う、または長期的な感情を経験した場合は、個人的にも専門的にも支援ネットワークを通じてサポートを求めることを推奨します。
スティグマとは何か?
スティグマとは、誰かがある特定の特徴や共有された属性を理由に、個人や集団を否定的に見るときに生じるものです。これはネガティブなステレオタイプであり、個人や集団に関する単純化された信念や考えを意味します(CCSA, n.d-d)。
差別とは、特定の特徴や共有された属性を理由に、個人や集団を否定的または有害に扱うことです。これはネガティブなステレオタイプから生じる行動です(CMHA, Ontario, n.d-d)。
人々は年齢、障害、宗教、ジェンダー・アイデンティティ、性的指向、人種、先住民アイデンティティ、住居の不安定さ、あるいは物質使用を理由にスティグマや差別を経験する可能性があります。個人が複数のアイデンティティや経験を持つ場合、ステレオタイプは複合的に作用することもあります。
物質使用に対するスティグマとは?
物質を使用する人、または過去に使用経験のある人々は、カナダや世界各地で強いスティグマ(偏見や差別)にさらされています。
2015年の「World Values Survey(世界価値観調査)」によると、「薬物使用障害をもつ人々は、他のどの集団よりもスティグマの対象となっており、回答者の約80%が『薬物使用障害のある人が自分の近所に住むのは望ましくない』と答えた」と報告されています(Stuart, 2019)。
物質を現在使用している人、あるいは回復過程にある人のどちらも、このスティグマの影響を受けます。スティグマは支援を求める意欲を奪い、医療・支援サービスへのアクセスを妨げます。その結果、適切なケアやサポートの質にも影響を及ぼします。
特定の薬物や使用方法によってスティグマの強さは異なります。
Paquette et al., 2018
例えば、オピオイドはアルコールよりも強くスティグマ化される傾向にあります。また、薬物を注射で使用する人は、喫煙など他の方法で使用する人よりも強いスティグマに直面します。
一部の人は、物質使用障害を「道徳的な失敗」や「個人の選択」、「犯罪行為」とみなすことがあります。しかし、物質使用障害は治療可能な健康状態であり、糖尿病や摂食障害と同様に医学的に認められた疾患です。
研究によれば、長期的または反復的な物質使用は脳の構造や機能を変化させ、意思決定能力や衝動抑制に影響を与えることが示されています(American Psychiatric Association, 2020)。
物質使用を道徳の問題とみなし、「スティグマを与えることで行動を改めさせる」と考える人もいます(Stuart, 2019)。しかしこの見方は、本人ではなく周囲の社会構造の問題を見逃してしまいます。
研究によると、こうした「スティグマを抑止策とする」方法は、物質使用の抑制には効果がなく、むしろ当事者に深刻な害を及ぼすことが分かっています(Lee & Boeri, 2017)。
演習
- あなたは振り返ってみて、物質使用障害のある人に否定的な態度を取ったことはありますか?どのようなことがありましたか? そのやり取りは相手にどのような影響を与えたと思いますか?
例
- 相手を差別的な言葉やスティグマを伴う言葉で表現すること、思いやりを欠いた接し方をすること、相手を批判すること
- 問題のある物質使用と物質使用障害について今知っていることを踏まえて、物質を使用する人について誤解していたことはありますか?
例
- 本人の選択
- 道徳的な失敗
- 本気で望めば治る
スティグマの種類
スティグマには3つの種類があります。
- 構造的スティグマ:学校を含む組織や制度の方針や慣行を通じて生じるもの
- 社会的または人間関係的スティグマ:家族、友人、日常生活で出会う人々から生じるもの
- セルフ・スティグマ
構造的スティグマ
構造的スティグマとは、特定の集団に属する人々を社会が過小評価し、その価値の切り下げが、差別的な制度・政策・慣行によって再生産され、正当化される現象を指します。
物質使用に対するスティグマから生じる世論や否定的なレッテル、誤解は、政策立案者の意思決定や資源配分に影響を与えます。その結果、サービスの提供状況、研究資金、法規制にも波及します(CCSA, n.d.-d)。
構造的スティグマは、以下のような不平等を生み出します。
- 医療への不平等なアクセス
- 住宅への不平等なアクセス
- 教育・就業機会の不平等
構造的スティグマの例
- 物質使用障害に関する研究や治療への資金が限られている(Families for Addiction Recovery, n.d-b)
- 他の健康状態と比較して治療の待機時間が長い
- ケアの質が低く、健康状態が悪化する(Public Health Agency of Canada, 2020a)
- 学校で物質の影響下にあった生徒を停学処分にするなどの懲罰的な対応
- 学校を拠点とした公衆衛生プログラムにおいて、物質使用や精神衛生上の問題に関する議論が避けられる
- 特定の物質使用の犯罪化。犯罪歴は雇用や住宅機会に影響し、貧困や住宅不安、絶望の連鎖を永続させる。
構造的スティグマの例:物質使用の犯罪化
親が物質使用で逮捕されると、子どもに壊滅的な影響を与える可能性があります。 児童福祉の実務(例:物質を使用する親から子どもを引き離すこと)や家庭裁判所制度は、 支援するのではなく、むしろ家族に恐怖や恥の感情を抱かせてしまう場合があります。
親が刑務所に入ることや、親の養育から引き離されることは、子どもの安全感や安定感を損ない、 将来的な物質使用やメンタルヘルスの問題のリスク要因となり得ます。
CCSA のオンライン教材 Insights on Substance Use(CCSA, n.d-e)では、さらに詳しい情報が提供されています。
社会的スティグマ
社会的スティグマ(対人スティグマ)は日常の相互作用の中で起こります。例として、物質を使用する人に否定的な態度を示したり、否定的な言葉で語ったりすることがあります。これは友人・家族・同僚など身近な人に限らず、医療従事者・救急隊員・政府関係者など公共サービスを提供する人からも生じます。
社会的スティグマの例
- 「ドラッグ中毒者」「ポットヘッド」といった否定的レッテル
- 「中毒者は怠惰で弱い」といった被害者非難のステレオタイプ
- 無視や軽視
- 「彼らは普通の人ではない」と考え、価値を低く見なす
- 映画・テレビ・SNSでの有害なステレオタイプ
- 劣悪な商品やサービスの提供
- 医療・社会サービス提供者による冷淡な対応
子どもや若者は周囲から学びます。教育者は包括的でスティグマのない言動を実践することで模範となれます。
メディアによるスティグマの刷り込み
メディアによる刷り込みは、物質使用に関するスティグマが私たちの社会で「当たり前」とされていく一因です。 メディアに登場するイメージは、大人や子どもに対して、メンタルヘルスの問題や物質使用障害を持つ人々について どのように考えるべきか、そしてそのような状態になった場合に何が起こるのかを刷り込みます。
映画やテレビ、SNSなどのメディアには、物質を使用する人々に関する有害なステレオタイプが描かれることがあります。 例えば、「路上生活者」や「捨てられた注射器」のイメージは、物質使用は社会的に疎外された人々にのみ起こるという 誤った思い込みを強化してしまいます。
Changing the Narrative は、否定的でステレオタイプ的なメディアの映像や表現の例を示すとともに、 メディアで物質使用について語る際に「ストーリーを変える」ために役立つ最新の情報、情報源、専門家(当事者としての経験を持つ人々を含む)を提供しています。
以下は個人的な自己省察です。グループで行う場合は、快適に共有できる範囲に留めてください。
演習
- 問題的物質使用を持つ人について、あなたの認識はどこから来たと思うか?
例
- メディア
- 友人
- 同僚
- 否定的なレッテルを使った経験はあるか?その時どう考え、今はどう感じているか?
例
- アル中
- ジャンキー
- 使用者
セルフ・スティグマ
セルフ・スティグマとは、他者から言われた否定的な言葉を本人が信じ込み、内面化してしまうことで、恥や自己嫌悪を抱く状態を指します。
子どもや若者は特に影響を受けやすい傾向があります。彼らにとって、同年代の評価や集団になじむことは重要です。見た目や振る舞いの「違い」を理由に、いじめや排除を受けると、自尊心や自己価値感が損なわれます。
脳の発達が続くこの繊細な時期に、否定的な自己イメージを内在化すると、健康や社会的な結果に長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。相談できる支援的な大人がそばにいない場合は、その影響がより大きくなります。
仲間から汚名を着せられた子ども・若者は、社会的孤立や生活の質の低下を経験することがあります。評価されたり、さらに汚名を着せられることを恐れて支援を求めないこともあります。これにより、不安やうつなどのメンタルヘルス問題が新たに生じたり悪化したり、ストレス対処として物質を使用する可能性が高まります。すでに物質を使用している若者では、セルフ・スティグマによって使用を隠したり、ひとりで使用したりするようになり、過量摂取など物質関連の害のリスクが高まり、支援にアクセスしにくくなります(Families for Addiction Recovery, n.d.-b)。
固定観念(ステレオタイプ)は、汚名を与える行動の一例です。 子どもは幼い頃から「オタク」「チャラい」「怪しい」などのレッテルを貼られやすく、それが思春期、さらには成人期まで尾を引くことがあります。ステレオタイプは、いじめを助長し、ストレスや不安につながることがあります。
セルフ・スティグマの例
- メンタルヘルスの問題があることで、恥ずかしい・気まずい・他人より劣っていると感じる。
- 自分の物質使用障害は自分の責任だと感じる。
- つらくても、助けを受けるに値しないと感じる。
- 誰も自分を気にかけていない、または自分は他人の負担だと感じる。
- 評価されることを恐れて、物質使用を隠す。
多くのメンタルヘルスの問題は青年期に始まるため、若者はスティグマを受けたり、 セルフ・スティグマを経験したりする高リスク群です。 しかし、セルフ・スティグマは学習によって形成されるものであるため、学び直して手放すことも可能です。
演習
- 私たちの社会でスティグマ化され得るアイデンティティ、特性、経験にはどのようなものがあるか?
例
- 体型
- 肌の色
- 宗教
- 学校でスティグマ的な行動はどのように現れるか?
例
- からかい
- いじめ
- 排除
- スティグマを受けることは人々にどのような気持ちを与えると思うか?
例
- 恥ずかしい
- 批判される
- 無価値だと感じる
交差的スティグマ
交差的スティグマ(複合的スティグマとも呼ばれる)は、ジェンダー・アイデンティティ、性的指向、物質使用、人種や先住民アイデンティティなど、複数の理由でスティグマを経験する場合に生じます。これらのスティグマが個人の中で交差し、スティグマや抑圧の経験を深め、悪化させます。
精神的健康状態の大半は青年期に始まるため、若者はスティグマやセルフ・スティグマを経験するリスクが高い一方で、セルフ・スティグマは学習されたものであるため、学び直すことも可能です。
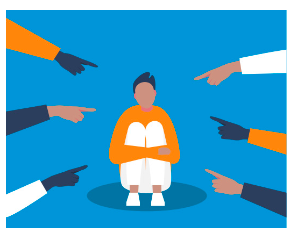
スティグマとジェンダー
物質を使用する人々に対するジェンダー化された見方は、個々人のスティグマ経験に影響を与えます。
Curry & Corral-Camacho, 2008
- 研究によると、物質を使用する女性や少女は「良い女の子」というジェンダー規範に従っていないとみなされ、 スティグマに直面します。妊娠中に物質を使用する女性は「道徳的欠陥がある」と批判され、 その結果、恥や罪悪感としてスティグマを内面化します(Lee & Boeri, 2017)。
- 男性は薬物関連犯罪で有罪判決を受ける可能性が高く、女性と比較してより厳しい刑罰を受ける傾向があります。
スティグマの影響
スティグマは支援を求める障壁となる
スティグマは、ウェルビーイングと良好な健康に対する大きな障壁です。若者は、恥をかかされたり他人から批判されたりすることへの恐れから、物質使用について話し合うことや、健康を回復するために必要な支援を求めたり受けたりすることを避ける可能性があります。その結果、家族や友人から孤立し、サービスへのアクセス能力や受けるケアの質にも影響が及び、物質使用障害の維持や再発リスクの増加にもつながります。
医療・社会サービス提供者が物質使用障害の複雑な原因を理解していない場合、保護者が自責感やセルフ・スティグマを抱き、地域社会から孤立することがあります(Families for Addiction Recovery, n.d-b)。
誤解に注意:「若者が薬物を使うのは自己責任であり、やめる気になればやめられる」
若者が物質の使用を始めるのは、時には本人にとって避けられない場合もあります。なぜなら、リラックスするため、あるいは精神的または身体的な苦痛を和らげるために使用を始めるからです。さらに、スティグマ(偏見)は物質使用を悪化させる可能性があります。なぜなら、偏見によって若者は助けを求めることができなくなり、使用頻度が増加する可能性があるからです。
Families for Addiction Recovery および Moms Stop the Harm は、親が子どもの問題的物質使用や物質使用障害を支援できるよう、知識・情報・リソースを提供する団体です。
スティグマはサービスの質に影響する
問題的物質使用や物質使用障害を持つ人々は、小売などの一般サービスや医療・社会サービス(政府職員、地域サービス提供者、医師、看護師など)から、劣悪な対応を受ける可能性があります。医療従事者の間でも、物質を使用する人々に対する否定的態度は一般的で(van Boekel ら, 2013)、用語選択により判断が変わることが示されています。例えば、「substance abuser(薬物乱用者)」と記述された場合は「substance use disorder(物質使用障害)のある人」と記述された場合よりも厳しく批判される傾向があります(Kelly ら, 2015)。カナダの医療システムにおける物質使用スティグマは、悪い健康結果に寄与します(van Boekel ら, 2013)。
サービスの質に影響を及ぼすスティグマの例には、以下のようなものがあります。
- 救急外来を受診した人は、物質を求めているだけだと思われたり、慢性疾患になったのは自業自得だと思われたりするために、迅速に診察を受けられない場合があります。
- 公共サービスの提供者から見下すような態度を取られたり、理不尽な扱いを受けたりすることで、物質使用者が今後その公共サービスの利用を避けるようになる可能性があります。
- 物質を使用する人が公共サービス提供者から批判的に見られていると感じたり、軽視されていると感じたりすると、受けるサービスやケアについて十分な情報に基づいた決定をするための質問をしなくなる可能性があります。
他の健康状態と同様に、問題的物質使用や物質使用障害を持つ個人は、利用可能な最も効果的な治療を受ける権利があります。
誤解に注意:「なぜ物質を使用する人々は助けを求めないのか?」
医療システムにおけるスティグマは、人々を孤立・拒絶・軽視されていると感じさせ、サービスの回避につながります。
スティグマは物質使用による害を増大させる
家族、友人、仲間から批判・スティグマ化されるという恐れは、若者に物質使用を隠し、孤立して使用する行動を促し、過剰摂取や薬物中毒といった害のリスクを高めます。
誤解に注意:「物質を使用する人は予測不能で危険だ。閉じ込めるべきだ。」
どのような背景の人でも問題的物質使用を経験し得ます。スティグマは語らう機会を奪い、孤立した使用を増やし、事故リスクを高めます。
言葉は重要
問題的物質使用や物質使用障害について話すとき、私たちが使う言葉は重要です。
- 特定の用語は無意識の態度・信念、理解・行動・決定に影響します(暗黙の認知バイアス)。
- 私たちの言葉は思考を形成し、他者の思考にも影響します。
- 言葉を変えることは、支援を求めやすくする第一歩になり得ます。
ハーバード医科大学の John Kelly 博士の研究では、「substance user(物質使用者)」と「substance abuser(薬物乱用者)」の用語の違いで、前者は「治療に値する」、後者は「処罰に値する」と見なされやすいことが示されました(Kelly & Westerhoff,
2010)。
これらの理由から人を優先する言葉(person-first language)を用いることが重要です。人間性を奪うラベルを語彙から外すことで、物質使用者の中心に「人」を見ることができます。
置き換えるべき用語の例
| 従来の用語 | 推奨される表現 |
|---|---|
| addict(薬物中毒者) | 物質使用障害のある人、または物質使用障害の経験のある人 |
| former addict(元薬物中毒者) | 物質使用障害の経験のある人 |
| binge drinker(大酒飲み) | 一過性大量飲酒をする人 |
| overdose(オーバードーズ) | 中毒(drug poisoning) |
| relapse(再発/挫折) | 使用の再発(recurrence of use) |
| recreational drug user(娯楽的薬物使用者) | 物質を私的に使用する人、または時折物質を私的に使用する人 |
説明例
差別的なレッテルではなく、より一般的で人を中心とした用語を使う理由を他者へ説明する必要があるかもしれません。その場合は、「物質を使用するすべての人々の尊厳を尊重し、物質使用障害の医学的性質に焦点を当て、害を与えるのではなく、ウェルビーイングを促進する用語」を使うことで変化をもたらしたいと説明してください(CCSA & Community Addictions Peer Support Association, 2019, p. 8)。
言葉を置き換える実例
用語を変更できるかどうかを考えるための例をいくつか示します。
| こうではなく | こう言い換えましょう |
|---|---|
| 「最近ずっと飲んでるじゃないか。なんでやめられないんだ?」 | 「最近飲酒が増えているように見えるけど、自分でも気づいてる?心配な点はある?もしあれば、私にできることはあるかな?」 |
| 「私は6か月間クリーンだ」 | 「私は6か月間、物質を使用していない」 |
| 「薬物乱用はあらゆる立場のカナダ人に影響を及ぼす」 | 「あらゆる立場のカナダ人が物質使用の影響を受けている」 |
| 「再発は回復を最初からやり直す必要がある」 | 「回復の道筋は直線的ではなく、変化に取り組む中で使用の再発が起こることもある」 |
| 「オーバードーズを見かけたらどうすればいい?」 | 「薬物中毒に苦しんでいる人を助ける方法を知ってる?」 |
| 「職場でハイになってる、解雇すべきだ」 | 「物質使用の問題があるかもしれない。従業員が安全・健康でいられるようにし、病気の人を支援する会社規定がありませんでしたか?」 |
| 「この人、アルコール臭いですね。いつも救急に来てるし、すぐに回復するでしょう」 | 「この方は物質を使用していた可能性があります。適切な診療を受ける権利があります。」 |
ストーリーを変えるための言い換え
問題のある物質使用や物質使用障害について他の人と話し合うときにどのように言い換えするかについて、いくつかの例を次に示します。
| こう聞かれたら | こう返事をしましょう |
|---|---|
| 「街中であんな依存症の人たちを見ると、どうして自分の人生を変えようとしないのか分かりません。もう少し自分を大切にすればいいのに。あんな生き方を選ぶなんて本当に不快です」 | 「誰かが私にこんなアドバイスをしてくれました。目の前に一生懸命生きてきた子どもがいると想像してみてください、と。そして、その子が成長する中でどんな困難に遭い、今どんな問題を抱えているからこれほど苦しんでいるのか考えてみるのです。そう考え始めると、あの人らは自分でも想像していなかった人生を生きているのだと気づきました。何か私たちにできることがあるかもしれません。少なくとも、一人の人間として敬意を持ち、その人自身を第一にした言葉遣いをすることはできます」 |
| 「フレッドがようやく戻ってきたな。28日間休んでたから、どこで何してたかは明らかだろ。もし俺がリハビリ施設に入れられたら、恥ずかしくて会社に戻って来れないけどな。よっぽど金に困ってるんだろう。持ち物には気をつけろよ」 | 「私もフレッドの体調を心配していました。彼が抱えている問題を理解したくて、物質使用障害について色々調べたんです。偏見が治療を受ける最大の障害の一つだって知っていましたか? 会社が物質使用障害もカバーする医療制度を提供しているのは、社員が適切な治療を受けられるようにするためなんです。健康問題で優秀な社員を失わないために。私はフレッドの復帰を歓迎して、彼を応援するつもりです」 |
| 「昨夜のスージー、どうかしてたよね。パーティー前には子どもたちがいるから早く帰らなきゃって言ってたのに、べろべろに酔っ払って帰ろうともしない。一緒にいて本当に恥ずかしかった」 | 「私には、スージーは家族と責任について考えていたように思えます。彼女の健康が心配でした。物質使用障害に関する資料を読んだところ、兆候の一つは自分の価値観に沿って行動する能力を失うことだそうです。この状態は深刻な健康問題のサインかもしれません。彼女に情報を共有するとともに、彼女の健康を心配していることを伝えるつもりです」 |
演習
- 「薬物中毒者(addict)」を「物質使用の経験者」に置き換えるなど、スティグマ的な言葉を一つ選び、より思いやりのある言葉で文を作る(CCSA, n.d-d)。
- 最近の物質使用者とのやり取りを振り返る。自分の言葉は助けになったか、妨げになったか?無意識のステレオタイプが影響したか?よりポジティブに言い換えられたか?
- 物質使用者をスティグマ化する場面に遭遇したと想像し、スティグマのない言葉や行動に変える方法を考える。
例
- 休日の夕食で家族が「薬物中毒者」を使う
- 軽いケガで救急外来にいるとき、酩酊しているように見える男性に対し、看護師が批判的な言葉を使う
教育者がスティグマを終わらせるためにできること
勇気を持ち、声を上げ、生徒にも同じことを促す
スティグマ的な態度や行動に立ち向かうには勇気が必要ですが、オープンな会話は障壁を取り除き、態度を変えるきっかけになります。
- 周囲の人が物質使用障害についてどのように話しているかに注意する
- スティグマ的な言葉を受け入れない姿勢を明確にする
- 人を優先し医学的に正しい言葉を使うよう促す
- 職場のスティグマ的な実践や方針に懸念を表明する
- スティグマに取り組む生徒の声やリーダーシップを支援する
セルフケアと自己受容を育む
ポジティブな自尊心を持つことは、若者のセルフ・スティグマ(自己への偏見)を軽減する助けになります。
教師は、生徒が意思決定や問題解決を行う際に支援し、学校や地域社会への貢献を促し、失敗を恐れずに学ぶことの大切さを伝えることで、自己肯定感を育むことができます(Brooks, 2009)。
詳細は下記をご覧ください。
How can teachers foster self-esteem in children
セルフケアを実践し、前向きな選択をすることも、子どもや若者にとって重要です。
Centre for Addiction and Mental Health(2019年)のポスターでは、以下のような
6つのセルフケア実践法
が紹介されています。バランスの取れた食事、十分な睡眠、体を動かすこと、人と話すことなど。
希望と共感を示す
物質使用障害が治療可能で、達成可能かつ持続可能なポジティブな結果がある健康状態であることを伝え、ステレオタイプではなく「人」を認める姿勢で共感を示します。
追加リソース
関連記事
|
マインドフルネス瞑想入門|専門家が解説する効果と実践法
公開:2025-02-20 04:25
マインドフルネス瞑想について
近年、病院で使われているマインドフルネス瞑想は、アメリカの医師ジョン・カバットジンさ…
|
|
|
大麻の効用 - ストレス解消
公開:2024-05-09 03:16
現代の忙しい社会では、ストレス(stress)がつきものです。仕事や家庭のプレッシャー、人間関係のトラブルなど、様々な要素がストレスを引き起こします。ストレスは…
|
|
|
大麻の効用 - 皮膚炎
公開:2023-10-30 22:11
肌トラブルの改善とカンナビノイドの関係について知りたいという思いで、「カンナビノイド 皮膚炎」で検索してきた皆さん、こんにちは。当ディスペンサリーストアの店…
|
|
|
教育者のための物質使用ガイド: 第5部「能力障害運転を理解する」
公開:2025-10-07 12:36
本ページの内容は、カナダ薬物使用・依存センター(CCSA) の資料「Unders…
|
|
|
教育者のための物質使用ガイド:イントロダクション
公開:2025-09-30 12:29
本ページの内容は、カナダ薬物使用・依存センター(CCSA) の資料「Un…
|
-
- CRDHとは?注目される新世代カンナビノイド成分の完全ガイド
- はじめに 近年、大麻由来成分に関する科学…
- 閲覧数:159
-
- 物質辞典 - CBXEとは
- 重要な前置き:本記事を執筆するにあたり、…
- 閲覧数:120
-
- 2025年CBN規制事件 - 更年期・PMSの緩和が違法になる日
- 更年期の不眠、PMSの痛み。やっと見つけ…
- 閲覧数:82
-
- 精製方法 - THCダイヤモンドの魅力を解説
- 大麻愛好家の皆さん、こんにちは。今回は大…
- 閲覧数:66
-
- 物質辞典 - 1S-LSD(規制物質)とは
- 1S-LSDは、2025年3月15日に厚…
- 閲覧数:64
-
- 物質辞典 - H4CBHとは
- 現代のウェルビーイングを追求する中で、日…
- 閲覧数:59
-
- 精製方法 - キーフの魅力と使い方を解説
- 大麻を愛する大人の皆さん、こんにちは。今…
- 閲覧数:48
-
- 海外 - ハワイのおすすめ大麻ディスペンサリー
- 目次 はじめに …
- 閲覧数:47